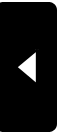2011年02月05日
こんなんじゃあ、犬も食わんな!
今日、妻とけんかした。ある喫茶店でゼンザイを食べたのだけれど、私は食べるのが早いという。せっかくおいしい物を食べるのに、味わってないと言われた。
「これがぼくの味わい方なんだよ。うまいものは、一番先に食べる。瞬間的に体全体で美味しさを感じるんだよ。ちまちま食べとったら、つまらん思いが入り込んで純粋に味わえない」
「なんで、そうヘリクツばかり言うの? 素直にまちがいを認めればいいのに」
妻はあきれた顔で、ゼンザイの白玉を口に運んだ。この「ヘリクツ」がまたカチンときた。
「ああ? へが理屈言うか? へが理屈言ったらトイレは理屈だらけだぞ。それになあ、犬はうまいものほど、あわてて食べるぞ。肉なんか、それこそ、飲み込むように食べるんだから。ぼくにはきっと犬のDNAが入っているんだ」
私は他にお客がいないのをいいことに大声を出した。私は犬が大好きだ。南総里見八犬伝なんぞ八房と犬塚信乃の犬が気の毒で楽しめないほどだ。先祖に2・3匹犬がいるんじゃないかとさえ思っている。
「犬? 犬が好きなのは分かるけど、犬っていい言葉ないよね。『犬死』『犬食い』って言うよね」
得意そうに言う妻はネコ派だ。
「ネコは猫舌っていうじゃないか。だから食べるのが遅いんだろ」
私がくやしまぎれに言い返すと、顔見知りの店の主人がテーブルを片付けながら仲裁に入った。
「そうそう、そういう夫婦ゲンカは犬も喰わないって言いますね」
もう一度言うけど、ほんとにゼンザイはうまかった。
「これがぼくの味わい方なんだよ。うまいものは、一番先に食べる。瞬間的に体全体で美味しさを感じるんだよ。ちまちま食べとったら、つまらん思いが入り込んで純粋に味わえない」
「なんで、そうヘリクツばかり言うの? 素直にまちがいを認めればいいのに」
妻はあきれた顔で、ゼンザイの白玉を口に運んだ。この「ヘリクツ」がまたカチンときた。
「ああ? へが理屈言うか? へが理屈言ったらトイレは理屈だらけだぞ。それになあ、犬はうまいものほど、あわてて食べるぞ。肉なんか、それこそ、飲み込むように食べるんだから。ぼくにはきっと犬のDNAが入っているんだ」
私は他にお客がいないのをいいことに大声を出した。私は犬が大好きだ。南総里見八犬伝なんぞ八房と犬塚信乃の犬が気の毒で楽しめないほどだ。先祖に2・3匹犬がいるんじゃないかとさえ思っている。
「犬? 犬が好きなのは分かるけど、犬っていい言葉ないよね。『犬死』『犬食い』って言うよね」
得意そうに言う妻はネコ派だ。
「ネコは猫舌っていうじゃないか。だから食べるのが遅いんだろ」
私がくやしまぎれに言い返すと、顔見知りの店の主人がテーブルを片付けながら仲裁に入った。
「そうそう、そういう夫婦ゲンカは犬も喰わないって言いますね」
もう一度言うけど、ほんとにゼンザイはうまかった。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
23:27
│Comments(2)
2011年02月05日
アリジゴクな日々
ある日、仕事から帰ると息子(小3)が満面の笑顔でよってきた。このパターンは何か頼みごとがあるに決まっている。
「ねえ。お父さん。今日学校でねえ宿題出された。あのさあ、来週までに理科の宿題で冬の昆虫を調べなくちゃいけないんだけど…」
と息子。
「冬の虫か? てんとう虫の冬越しに、あとはミノムシ、イラガのまゆでも探しにいくか。日曜日に」
ビールをあけながら答える私。
「だめ、だめ。そんなベタなネタじゃあ笑いがとれんよ」
「はあ? 学校の宿題にベタもなにもないだろ? なんで笑いをとらないかんの?」
「だからさあ、ぼくにも『アマチュア落語家の息子』としてのプライドがある。授業中1回はみんなをびっくりさせて、笑いをとらんとつまらん」
そういって、私のビールをとりあげてグラスに注いでくれた。こっちも悪い気はしない。
「なにか、考えがあるのか?」
思わず、話に乗ってしまった。
「さすがお父さん。あのねえ。アリジゴクがほしい」
目を輝かせる息子。その向こうから冷ややかな視線を送ってくる妻。
「アリジゴク? そんなのどこにいるんだよ」
私は声をひっくり返した。ビールどころじゃない。息子は昆虫図鑑を持って走ってくる。
「あのねえ、雨のあたらない、さらさらの砂のところにいるんだって。お寺の軒下とか川の橋の下だって」
「ふううん。そうか、さがしてみるか」
かくして、息子は地図、私はインターネットのマップページを探し、妻は知り合いに電話しまくり、まさしく家庭内探偵ナイトスクープ状態に陥る事50分。豊川の橋、豊川稲荷の奥の院、砥鹿神社、財賀寺、宮路山、とリストアップできた。
そして、日曜日。豊川稲荷から回っていく、×。豊川の橋、下条、当古、三上、加茂まとめて×。砥鹿神社、×。
夕方、あきらめかけていた宮路山の展望台の下であこがれのアリジゴクをゲットした。プラスティックの水槽にたっぷり砂を入れて持ち帰るとしっかりすり鉢状の巣を作った。
めでたし、めでたしと思いきや。
「ねえ、アリジゴクってなに食べるんだっけ?」
妻がポツリと言った。
「そんなの決まってるよ。アリじゃないか」
と息子。
「アリ? どこにいる? この冬に」
と妻。もしかして、今度は冬の寒空のもとでアリ探し? もう夕方だし! 気が遠くなり、アリジゴクに落ちたアリの気持ちが分かってきた。
「だいじょうぶだよ。あのねえ、アリジゴクって2ヶ月くらい餌がなくても死なないらしいよ」
息子の明るい声が、ひとすじの光明に感じられた。2ヶ月の執行猶予があれば…、4月になれば…、アリが出てくる。
「でもさあ、このアリジゴクが、今日えさを食べたならいいけどさあ、最後にえさを食べたのが、2ヶ月前だったら?」
妻の一言で、私と息子はまた「アリジゴクの巣」の真ん中に落ちていくのであった。
「ねえ。お父さん。今日学校でねえ宿題出された。あのさあ、来週までに理科の宿題で冬の昆虫を調べなくちゃいけないんだけど…」
と息子。
「冬の虫か? てんとう虫の冬越しに、あとはミノムシ、イラガのまゆでも探しにいくか。日曜日に」
ビールをあけながら答える私。
「だめ、だめ。そんなベタなネタじゃあ笑いがとれんよ」
「はあ? 学校の宿題にベタもなにもないだろ? なんで笑いをとらないかんの?」
「だからさあ、ぼくにも『アマチュア落語家の息子』としてのプライドがある。授業中1回はみんなをびっくりさせて、笑いをとらんとつまらん」
そういって、私のビールをとりあげてグラスに注いでくれた。こっちも悪い気はしない。
「なにか、考えがあるのか?」
思わず、話に乗ってしまった。
「さすがお父さん。あのねえ。アリジゴクがほしい」
目を輝かせる息子。その向こうから冷ややかな視線を送ってくる妻。
「アリジゴク? そんなのどこにいるんだよ」
私は声をひっくり返した。ビールどころじゃない。息子は昆虫図鑑を持って走ってくる。
「あのねえ、雨のあたらない、さらさらの砂のところにいるんだって。お寺の軒下とか川の橋の下だって」
「ふううん。そうか、さがしてみるか」
かくして、息子は地図、私はインターネットのマップページを探し、妻は知り合いに電話しまくり、まさしく家庭内探偵ナイトスクープ状態に陥る事50分。豊川の橋、豊川稲荷の奥の院、砥鹿神社、財賀寺、宮路山、とリストアップできた。
そして、日曜日。豊川稲荷から回っていく、×。豊川の橋、下条、当古、三上、加茂まとめて×。砥鹿神社、×。
夕方、あきらめかけていた宮路山の展望台の下であこがれのアリジゴクをゲットした。プラスティックの水槽にたっぷり砂を入れて持ち帰るとしっかりすり鉢状の巣を作った。
めでたし、めでたしと思いきや。
「ねえ、アリジゴクってなに食べるんだっけ?」
妻がポツリと言った。
「そんなの決まってるよ。アリじゃないか」
と息子。
「アリ? どこにいる? この冬に」
と妻。もしかして、今度は冬の寒空のもとでアリ探し? もう夕方だし! 気が遠くなり、アリジゴクに落ちたアリの気持ちが分かってきた。
「だいじょうぶだよ。あのねえ、アリジゴクって2ヶ月くらい餌がなくても死なないらしいよ」
息子の明るい声が、ひとすじの光明に感じられた。2ヶ月の執行猶予があれば…、4月になれば…、アリが出てくる。
「でもさあ、このアリジゴクが、今日えさを食べたならいいけどさあ、最後にえさを食べたのが、2ヶ月前だったら?」
妻の一言で、私と息子はまた「アリジゴクの巣」の真ん中に落ちていくのであった。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
00:40
│Comments(4)
2011年02月05日
草砥鹿姫が現代へ
草砥鹿姫は弁財天に乗り移って、三明寺を三河を今も守っている。では、豊川を竜に変えた青い石はどこへ行ったのだろう。この話になると1300年前にもどらねばならない。彼女は当時としては大変長生きで90歳くらいまで生きたらしい。死ぬ間際に肌身離さず持っていた青い石を、豊川の岸に埋めたという。そのまま川岸で生き絶えたと伝えられている。
時を越えて青い石は豊川の河原に眠っていたのだが、昭和の終わりごろ、ひょんなことから眠りからさめることとなった。川岸に公園を作ることになって土を掘ったのだが、その土は水はけがよいことからある小学校のグランドへ運ばれた。その中にこの石がまじっていたのだ。
石は何年か小学校のグランドに埋まっていた。
ある夏の朝、男の子が学校へくると、朝日に光る青い石をみつけてポケットにしまった。1300年の時をこえてここから物語が動きはじめるのだ。もう誰にもとめられない。
時を越えて青い石は豊川の河原に眠っていたのだが、昭和の終わりごろ、ひょんなことから眠りからさめることとなった。川岸に公園を作ることになって土を掘ったのだが、その土は水はけがよいことからある小学校のグランドへ運ばれた。その中にこの石がまじっていたのだ。
石は何年か小学校のグランドに埋まっていた。
ある夏の朝、男の子が学校へくると、朝日に光る青い石をみつけてポケットにしまった。1300年の時をこえてここから物語が動きはじめるのだ。もう誰にもとめられない。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
00:30
│Comments(0)
2011年02月04日
一人餅つきのすすめ
立春です。春です。昨日は旧正月でした。そこで餅つきをしましょう。臼がない。杵がない。餅つき機がない。
それでも炊飯器はあるでしょ? もち米を炊飯器で炊いて、すり鉢か、なければどんぶりに入れてすりこ木、これもなければスプーンでつぶします。一人分ぐらいなら10分もかからずに餅になります。つき具合もお好みでできます。あとは、黄粉をかけるなり、海苔しょうゆなりお好みでどうぞ。
これ、子どもは案外よろこんでやりますよ。
気に入った場合は、すり鉢も、すりこ木も、100円ショップにあります。「一人餅セット」をそろえましょう。
お試し下さい。
それでも炊飯器はあるでしょ? もち米を炊飯器で炊いて、すり鉢か、なければどんぶりに入れてすりこ木、これもなければスプーンでつぶします。一人分ぐらいなら10分もかからずに餅になります。つき具合もお好みでできます。あとは、黄粉をかけるなり、海苔しょうゆなりお好みでどうぞ。
これ、子どもは案外よろこんでやりますよ。
気に入った場合は、すり鉢も、すりこ木も、100円ショップにあります。「一人餅セット」をそろえましょう。
お試し下さい。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
08:52
│Comments(4)
2011年02月03日
万葉集の話5
利修仙人も3匹の鬼も、草砥鹿姫も三河の国の守り神となって時代は下る。
草砥鹿姫の眠る三明寺には平安朝の国司、大江定元が弁財天を奉納した。モデルになったのは若くしてなくなった妻、力寿姫。その美しい姿は草砥鹿姫に似ていた。この力寿姫、実は草砥鹿姫が生まれ変わったのであるが、それを知っているものはいない。
時はすぎて鎌倉に幕府が出来ると、むさ苦しい男たちは東をめざす。姫街道は鎌倉街道と名前をかえた。
幕府に味方しない三明寺に男たちは火を放った。メラメラと上がっていく炎。いよいよ弁財天に火がかかろうとしたその時、弁財天は立ち上がった。
「おまえたちのような、力にのみ頼るものに、私を焼く力なぞないわ」
弁財天は炎の中で舞い踊りながら高らかに笑った。天女のように宙もまいながらビワをひくと兵たちはその場に座りこんだ。空は急に曇り大粒の雨が落ちだした。地面からはあそこからここから水が湧き出した。見る見る間に火は消え、弁才天はなにごともなかったように木の象にもどった。
草砥鹿姫が乗り移った弁財天が予言した通り、鎌倉幕府は力をなくし後醍醐天皇により倒された。その後通りかかった天皇の皇子、無文禅師により三明寺は再興された。
そのあと、南北朝の騒乱でまた世の中は荒れたが三明寺に手をかける者はいなかったという。
草砥鹿姫の眠る三明寺には平安朝の国司、大江定元が弁財天を奉納した。モデルになったのは若くしてなくなった妻、力寿姫。その美しい姿は草砥鹿姫に似ていた。この力寿姫、実は草砥鹿姫が生まれ変わったのであるが、それを知っているものはいない。
時はすぎて鎌倉に幕府が出来ると、むさ苦しい男たちは東をめざす。姫街道は鎌倉街道と名前をかえた。
幕府に味方しない三明寺に男たちは火を放った。メラメラと上がっていく炎。いよいよ弁財天に火がかかろうとしたその時、弁財天は立ち上がった。
「おまえたちのような、力にのみ頼るものに、私を焼く力なぞないわ」
弁財天は炎の中で舞い踊りながら高らかに笑った。天女のように宙もまいながらビワをひくと兵たちはその場に座りこんだ。空は急に曇り大粒の雨が落ちだした。地面からはあそこからここから水が湧き出した。見る見る間に火は消え、弁才天はなにごともなかったように木の象にもどった。
草砥鹿姫が乗り移った弁財天が予言した通り、鎌倉幕府は力をなくし後醍醐天皇により倒された。その後通りかかった天皇の皇子、無文禅師により三明寺は再興された。
そのあと、南北朝の騒乱でまた世の中は荒れたが三明寺に手をかける者はいなかったという。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
23:48
│Comments(0)
2011年02月03日
落語ダイエット?
もしよかったら落語やって見ませんか? 落語は見ている簡単そうに見えてじつは簡単です。日常会話程度の日本語ができれば出来ます。
お腹から声を出すので健康にいいし、しゃべっている間は物を食べられないのでダイエットになります。
また、人前でやると冷や汗はかくし、うけなければ身を削る思いがするのでこれもダイエットになります。
まず座布団に座って、背筋をのばしましょう。左の方を向いて「こんちわ」と叫びましょう。恥ずかしがっては負けです。今度は右を向いて「ああ、いらっしゃい。まあ上がっとくれ」。
これで完成です。ねっ簡単でしょ。あとはネタを仕入れます。子どもさんが小学生の場合は3年生の国語の教科書に「寿限無」がのっていますし、図書館でも落語絵本がたくさんあります。憶えるのは大変でも、話の流れだけ頭に入れてあとは適当に会話に進めて行きましょう。
もう、あなたはアマチュア落語の真打です。メールいただければ出演先紹介しますよ(笑)。ただし、ギャラは出ません。あしからず…
お腹から声を出すので健康にいいし、しゃべっている間は物を食べられないのでダイエットになります。
また、人前でやると冷や汗はかくし、うけなければ身を削る思いがするのでこれもダイエットになります。
まず座布団に座って、背筋をのばしましょう。左の方を向いて「こんちわ」と叫びましょう。恥ずかしがっては負けです。今度は右を向いて「ああ、いらっしゃい。まあ上がっとくれ」。
これで完成です。ねっ簡単でしょ。あとはネタを仕入れます。子どもさんが小学生の場合は3年生の国語の教科書に「寿限無」がのっていますし、図書館でも落語絵本がたくさんあります。憶えるのは大変でも、話の流れだけ頭に入れてあとは適当に会話に進めて行きましょう。
もう、あなたはアマチュア落語の真打です。メールいただければ出演先紹介しますよ(笑)。ただし、ギャラは出ません。あしからず…
Posted by ひらひらヒーラーズ at
10:30
│Comments(0)
2011年02月03日
万葉集の話4
一方の草砥鹿姫、黒人を思う気持ちが強く食事ものどを通らない。日に日にやせていく。
そんなある日、利修仙人の夢を見る。都で黒人が病にふせっているという。
なんとか自分を都へつれて行ってほしいと頼むが、利仙人も鬼ももうこの世の者ではない。
それでも「せめてひと目会いたい」という姫に、夢の中の利修仙人が青い石を渡す。
「これで、豊川を竜にかえて都まで飛ぶがいい」
夢から覚めた姫の手には夢で見た石があった。姫は一人本宮山に登り豊川に向けて青い石をかざす。豊川は下流が竜の頭、今の長篠のあたりが尻尾の大きな竜になり草砥鹿姫を乗せて大空へと舞い上がった。
都へ着くと、黒人も草砥鹿姫への思いが強くあまりの切なさに寝込んでいたという。草砥鹿姫は黒人とともに2年をすごす。やがて天皇が崩御し、黒人も病でなくなった。
傷心の草砥鹿姫は、風の噂に、三河の国が飢饉で苦しんでいると聞く。豊川を竜として連れてきてしまったため、水不足が原因らしい。
「自分の恋のために、人々を苦しめてしまった。自分は神をまつる巫女であるのに、人々を苦しめ神にもそむいてしまった。この上は国にもどって国を守ることに命をささげよう」
そう誓った姫は三河の国にもどって竜を川にもどして懐かしい二見の道のあたりでくらし静かに一生終えた。今の三明寺のあたり1300年前の話である。
そんなある日、利修仙人の夢を見る。都で黒人が病にふせっているという。
なんとか自分を都へつれて行ってほしいと頼むが、利仙人も鬼ももうこの世の者ではない。
それでも「せめてひと目会いたい」という姫に、夢の中の利修仙人が青い石を渡す。
「これで、豊川を竜にかえて都まで飛ぶがいい」
夢から覚めた姫の手には夢で見た石があった。姫は一人本宮山に登り豊川に向けて青い石をかざす。豊川は下流が竜の頭、今の長篠のあたりが尻尾の大きな竜になり草砥鹿姫を乗せて大空へと舞い上がった。
都へ着くと、黒人も草砥鹿姫への思いが強くあまりの切なさに寝込んでいたという。草砥鹿姫は黒人とともに2年をすごす。やがて天皇が崩御し、黒人も病でなくなった。
傷心の草砥鹿姫は、風の噂に、三河の国が飢饉で苦しんでいると聞く。豊川を竜として連れてきてしまったため、水不足が原因らしい。
「自分の恋のために、人々を苦しめてしまった。自分は神をまつる巫女であるのに、人々を苦しめ神にもそむいてしまった。この上は国にもどって国を守ることに命をささげよう」
そう誓った姫は三河の国にもどって竜を川にもどして懐かしい二見の道のあたりでくらし静かに一生終えた。今の三明寺のあたり1300年前の話である。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
09:52
│Comments(0)
2011年02月02日
今日は小学校で落語
今日は息子の通う小学校の読み聞かせの日、白宮は、5年1組で落語をやってきました。演目は「うしほめ」みんな恐ろしく笑っていました。あのあと、授業になったのかなあ…?
来週の火曜日はお稲荷さんの近くの小学校で「語りの会」をやります。これ楽しいですよ。子どもたちが地元の民話や伝承を取材してきてまとめたのを、しらみやがメチャクチャにして子どもたちと先生を困らせ?ます。もう5年目になりますが、子どもたちはノリがいいです。

来週の火曜日はお稲荷さんの近くの小学校で「語りの会」をやります。これ楽しいですよ。子どもたちが地元の民話や伝承を取材してきてまとめたのを、しらみやがメチャクチャにして子どもたちと先生を困らせ?ます。もう5年目になりますが、子どもたちはノリがいいです。

Posted by ひらひらヒーラーズ at
21:09
│Comments(0)
2011年02月02日
万葉集3
ヌエを退治した利修仙人たちは三河にもどってきた。ヌエの死体を石巻山の中ふくに埋めると、京塚をたて封じた上で、本宮山頂に鏡岩をおいた。怪力の鬼たち3匹は岩の角度を何度も直して半年がすぎ、あくる年の夏至の朝、反射した光が石巻山の経塚にあたるようにした。
ヌエは夜の化け物、日の光に弱いため、年に一度一番日に力が強くなる夏至に鏡岩から集められた光をあてられ復活を防ぐ。この時の光の帯を見た後の人々は石巻山と本宮山が背比べをしていると思ったという。
このあと、利修仙人は神となり国をまもろうと、3匹の鬼の首をはねて鳳来寺山に埋めると自分も静かに命を終わらせた。
この、利修仙人にヌエ退治を頼みに来るのが持上皇の旅の目的だった。持統と共にやってきた高市連黒人が三河の国一宮の宮司草砥鹿氏に頼み実際に山の神と話ができる草砥鹿姫が利修仙人を呼び出したのだ。
仕事を終えた一行は、都へ帰るべく姫街道を東へと向かう。今の三明寺の坂を越えたあたりで草砥鹿姫と黒人の別れがあったと思われる。
黒人が歌う
妹もわれも 一つなれかも 三河なる 二見の道ゆ 別れかねつる
草砥鹿姫が返す
三河の二見の道ゆ 別れなば和が背も我も 一人かもゆかむ
ヌエは夜の化け物、日の光に弱いため、年に一度一番日に力が強くなる夏至に鏡岩から集められた光をあてられ復活を防ぐ。この時の光の帯を見た後の人々は石巻山と本宮山が背比べをしていると思ったという。
このあと、利修仙人は神となり国をまもろうと、3匹の鬼の首をはねて鳳来寺山に埋めると自分も静かに命を終わらせた。
この、利修仙人にヌエ退治を頼みに来るのが持上皇の旅の目的だった。持統と共にやってきた高市連黒人が三河の国一宮の宮司草砥鹿氏に頼み実際に山の神と話ができる草砥鹿姫が利修仙人を呼び出したのだ。
仕事を終えた一行は、都へ帰るべく姫街道を東へと向かう。今の三明寺の坂を越えたあたりで草砥鹿姫と黒人の別れがあったと思われる。
黒人が歌う
妹もわれも 一つなれかも 三河なる 二見の道ゆ 別れかねつる
草砥鹿姫が返す
三河の二見の道ゆ 別れなば和が背も我も 一人かもゆかむ
Posted by ひらひらヒーラーズ at
11:45
│Comments(0)
2011年02月01日
万葉集の話2
草砥鹿姫は、本宮山の神を祭る巫女だった。そこへわざわざ持統天皇ご一行がたずねて来たのはなぜか、もちろん観光旅行などではない。持統天皇(この当時もう上皇)は59歳、行幸が終わって都へもどって1月でなくなっている。体はかなり弱っていたはずだ。よほどの理由があったのだろうが、日本書紀に一言も書いてない。
一方、鳳来寺山の利修仙人。先代の天武の頃から鬼3匹を従えて修行をしていたという。鳳凰に乗り、空中暴走族よろしく三河の空にとどまらず日本中を飛び回っていたという。
ある日、本宮山の巫女草砥鹿姫がたずねてくる。都から持統上皇の一行が来ているという。文武天皇が病気になった。どうも誰かのたたりらしい。なんとか助けてほしい。
3匹の鬼をつれた利修仙人、都へ飛んでヌエをいう怪物を退治した。
一方、鳳来寺山の利修仙人。先代の天武の頃から鬼3匹を従えて修行をしていたという。鳳凰に乗り、空中暴走族よろしく三河の空にとどまらず日本中を飛び回っていたという。
ある日、本宮山の巫女草砥鹿姫がたずねてくる。都から持統上皇の一行が来ているという。文武天皇が病気になった。どうも誰かのたたりらしい。なんとか助けてほしい。
3匹の鬼をつれた利修仙人、都へ飛んでヌエをいう怪物を退治した。
Posted by ひらひらヒーラーズ at
21:14
│Comments(0)